私たちが「この人、目が笑っていない」と感じるのはなぜ?

―生物のコミュニケーションを研究されていると伺いました。
全人類の種族、文化圏を見ても「笑顔なのに、実はマジ切れしている」「マジ切れしている表情なのに、実は超楽しんでいる」という文化は見つかっていません。つまり、その種にとって「感情の表出」は普遍的なものだと考えられます。
笑顔の人を見たときに「この人口角は上がっているけど、目は笑っていない」と感じたことはないでしょうか。人間は、目の周りの表情筋を意図的にはほぼ動かせないんです。つまり、感情の表出はほぼコントロールできない。じゃあ、私たちはなぜそれほど正直に感情を出してしまうのか。これが、僕が動物から人類まで含めた生物に対して抱いている興味なんです。
感情の表出をコントロールできないのは、生物の進化として、感情がある程度相手に伝わることが必要だった(適応的だった)ということ。群れをなす動物では、ある個体が天敵を見つけて声を出すと、他の個体も一斉に逃げることがありますよね。生物がシグナル(信号)を出すのは、相手の行動を変えるためだと考えられます。シグナルを受け取った周りの個体の行動が変わる。それによって、関係性や互いの状況がよくなる。そうやってコミュニケーションは進化していったはずです。そのようなやりとりが可能な個体が、環境に適応できることが多かった。そうやって現れた種の中に、ヒトも含まれるはずです。
―なぜ我々は感情を出してしまうのか、改めて考えてみると興味深いですね。具体的にはどのような研究をされているのでしょうか。
マウスを用いた音声コミュニケーションと、それらの現象の神経メカニズムを研究しています。マウスは、遺伝子改変の技術が進んでいますし、寿命が短いので哺乳類の中では研究に用いやすい動物なんですが、感情表現の研究対象としてはあまり面白くなさそうですよね。でも実はマウスは鳥が歌うように複雑な超音波を出しているんです。僕の研究では特に求愛の声を扱っています。
以前は数分間の音源を解析するのに1~2時間かかっていたんですが、鳥の音声コミュニケーションの研究者との共同研究により、鳥用のシステムをマウス用に転用してもらったことで、音源の1.5倍くらいの時間での解析が可能になりました。おかげで、卒論指導でも助かっています。コミュニケーションの研究なので、どちらの個体が鳴いているかを見分けることも重要です。いま、そのための技術開発にも共同研究で挑戦しています。
「世界の一端を知れた」瞬間を味わいたい

―研究をしていて、どんなときに嬉しさを感じたり、興奮を覚えたりしますか。
僕の研究者人生で数回しかないんですが、一つはポスドク研究員時代です。オスがメスに対して超音波発声をしているとき、メスに対するモチベーションも上がっていると考え、「メスと会わせたときにドーパミン神経が活性化しているオスは、超音波発声をしている」という仮説のもとに実験をしたら、まったくその通りだった。初めて「研究というのは、こうやってうまくいくのか」と知りました。
いまは、学生さんと一緒に研究をしているのですが、まだ報告されていない未知の鳴き声を探したりもしています。アイデアを一緒に練って、実験していくわけですが、ここ数年ですでに2つくらい見つけられました。僕の気分としては大分満足しているのですが、研究としてはいろいろ詳細を詰めていかないといけないので、下の学年に引き継いで研究を深めているものもあります。その現象を初めて見つけたときが、一番わくわくしますが、科学の知見としてまとめていく仕事は時間がかかるので、つらい面もあります。早く論文として発表してしまいたいです。
僕の気持ちが動くのは「世界の一端を知れた」と思える瞬間。それは多分、研究じゃなくても同じなんです。
―研究以外で、「世界の一端を知れた」と感じるのはどんなときですか。
例えば、釣りでしょうか。未知の異世界に自らキャストする(仕掛けを飛ばす)。この辺に仕掛けを落として、竿を動かしてみたけど、本当に魚が来るかはわからない。でも魚からの反応があった瞬間に「ああ、正しかったんだ」とわかるじゃないですか。知識レベル、論理レベルの発見と、「僕自身の予想通りだった」という手応えや感触とでも言うべき実感は、別次元の楽しさですね。「ああ、世界はこうなっている」って知った瞬間に、生きているって思うのかな。研究では、統計解析をしたり論文を書いたりしているときよりも、実験結果がリアルタイムで分かる作業をしているときに、この実感を得やすいですね。
―先生は宮城県仙台市出身ということですが、鹿児島で科学を研究していることの強みや魅力を感じることはありますか。
鹿児島は、「自然の法則が確かに存在している」ということを実感しやすい土地だと思います。桜島に雲がかかることで、雲には影があることがよくわかる。日々桜島を見ていると、季節によって太陽が昇る位置が変わることも実感できます。
甲突川に釣りに行くんですが、満潮のときには水面付近だけ逆流します。最初に逆流の様子を見たとき、え?なに?と思いましたが、「ああ満潮か。これは自然の法則上、起こり得ることなんだな」と理解しました。鹿児島に来て、自然は本当に我々の身近にあるということを常に強く感じています。
自分は「科学者」であり、「社会の一員」でもある
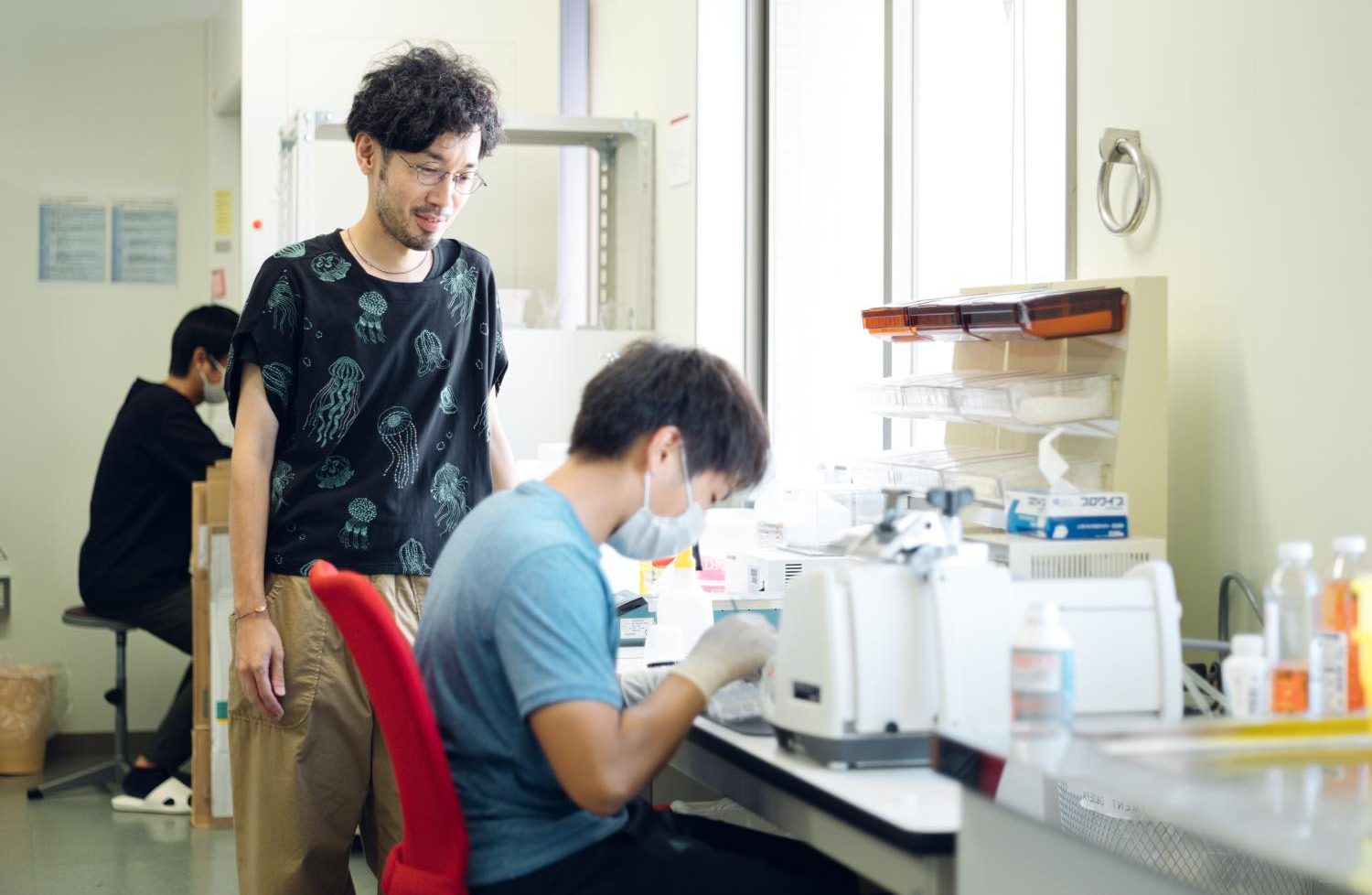
―先生は、サイエンスコミュニケーション(科学の面白さや科学技術に関する課題を人々へ伝え、ともに考え、意識を高めることを目指した活動)にも熱心に取り組まれていますね。
僕の専門分野は、生物学をバックグラウンドとした神経科学。「あなたの研究は、私たちの生活とどんな関わりがありますか?」と問われると、研究と社会との距離が遠すぎて、結構苦しい部分があります。一方で、社会的な意味を度外視して研究するからこそ、明らかになることも数多くある。
社会から少し隔絶されている科学者としての自分。この社会に生きるイチ市民、アクターとしての自分。僕にはその2つの人格があるんです。科学者としての自分をどうやって社会と接続していくべきかは、ずっと迷っていて。その折り合いのつけ方として、サイエンスコミュニケーションをしているんだと思います。
―社会との関わりという中には「教育」も含まれると思います。研究と教育の2つの役割を持つ大学で、両立に悩む教員は少なくないのではないでしょうか。
僕も2つの自分の間で苦しんでいるんですが、この対話から逃げていると、きっと新しい研究はできないんです。学生から研究テーマを相談されたとき、「うちの研究室ではその実験はできません」と断って終わりだと、僕は今の僕のままで、変わらないですよね。「それは無理じゃないかな…」と思っても、「でもこれをこうすればできるかも」と考えられると、僕も新たに勉強しますし、研究室で扱える実験やテーマが増えていく。この繰り返しが僕の研究の幅、可能性を広げていると言えるかもしれません。
僕は今、どんな研究者になろうか模索している真っ最中なんですよ。学生に教えると同時に、僕自身がどう成長していけばいいのか探っているところです。
大学は、教育機関でも研究機関でもある。「研究」「教育」「社会とのつながり」の循環がつくれるのは大学の強みです。研究をすることが教育リソースになり、教育をしたから社会との接点ができて、社会との接点ができると、それが大学独自の研究リソースになる。その循環を生むことが、それぞれの土地に教育基盤を持つ意義だと考えています。
―これまで授業を公開することに抵抗があったと伺っています。今回初めて公開授業に手を挙げられたのはなぜですか。
「今の僕なら、社会人の受講生の期待にもある程度応えられるかもしれない」と思えるようになったからでしょうか。
担当するのは「神経科学」という科目で、行動を制御する脳の機能について解説します。科学者としての僕が、人文社会系の分野を専門とする学生さんに伝えられることを絞り出して作ってきた授業です。心理学の学生さん向けの専門の授業としての側面と、他の専門の学生さんにとっての教養的な内容の側面の両立を目指しています。基礎的な内容ですから、一般の方にも興味を持ってもらえる自信がなくて、公開するのが怖かったんですね。でも、学生向けの授業を重ねるうちに、少なくとも若い人の共感は得られていると自負できるようになりました。公開授業に挑んでも、そろそろ大丈夫じゃないかなと思えたんです。
―授業の具体的な内容を教えてください。また、どんな方におすすめしたいですか。
前半は、基礎的な神経科学の話ですが、後半は僕の研究テーマである「マウスの音声コミュニケーションと脳のメカニズム」から、生物の2個体間、3個体間、集団、社会についての話に展開していきます。人と動物、人と人の比較を通して、他者と自分との境界、その間のグラデーションについて常に問い続ける構成になっています。
興味を持ってもらえるような仕掛けとしては、SF作品『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』や『ハーモニー』、『彼女は一人で歩くのか?』などを題材に、神経科学や生物学の発展によって生じうる社会問題について取り上げます。受講生の皆さんには授業で学んだ知識を活かして、「この作品のような近未来は、起き得るのか?起き得ないのか?」「今の技術では、どの程度現実味があるのか?」、「作品で描かれているような世界を自分は望むか?」ということを考察していただきたいです。
「自己と他者の関係」「自分の常識・認識は、他者とどれほど異なり、どれほど一致するのか」―。そんなテーマに興味がある方には、面白く感じていただける授業になると思います。
(インタビュー実施日:2021/10/11)
※撮影のため、発声していない状態でマスクを一時的に外しています。


